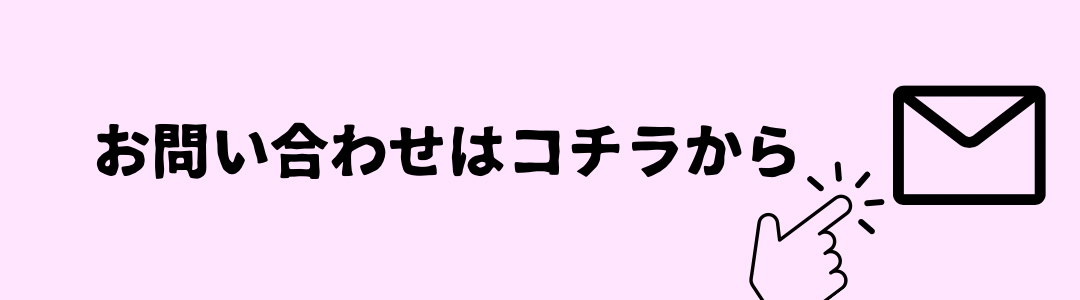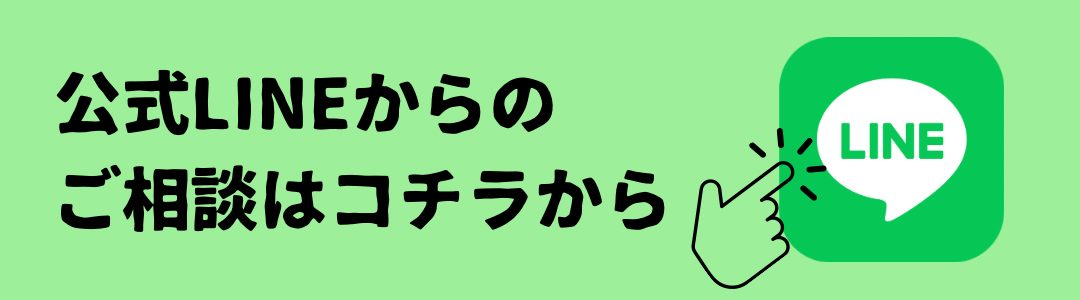【癇癪を繰り返す子どもへの対応策!】家庭教育の目的と役割を考える
ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
今回は、「子どもの癇癪と家庭教育の目的」についてです。
子どもが癇癪を起こす場面は、親として非常に頭を悩ませるものです。例えば、「自分でうまくいかない」「思い通りにいかない」など、日常のちょっとしたきっかけが、癇癪へとつながることが多々あります。こうした癇癪は、実は家庭教育の在り方と深く関係しているのです。
【家庭教育とは】
家庭教育は、学校教育や地域教育と並ぶ教育の3本柱のひとつです。その中でも特に家庭教育が果たす役割は、 子どもが家庭内で身につける生活習慣や価値観、コミュニケーション能力、自立心、社会性を育む教育のことです。これらは、癇癪をコントロールする能力を身につけるためにも不可欠な要素です。
学校教育や地域教育と並ぶ重要な柱のひとつで、食事や身だしなみ、マナーなどの日常的な習慣から、感情のコントロールや人間関係の築き方まで、多岐にわたる内容を含みます。
家庭教育の目的は、子ども自身が「親がいなくても自立して生きていける力」を養うことにあります。そのため、過保護や過干渉を避け、子ども自身が考え行動できるよう育てることが求められます。
【癇癪が起きる原因と家庭教育の役割】
NEO PORTAには、癇癪に悩む親御さんから以下のような相談が寄せられます。
・「子どもが思い通りにならないと癇癪を起こす」
・「少しの失敗で激しく怒る」
・「友達と衝突しやすい」
・「自分の気持ちをうまく言葉で表現できない」
これらの背景には、自立心や自己肯定感の未成熟が隠れています。癇癪を起こす子どもたちに共通するのは、常に心の中で自分時自身が「どうしていいかわからない」状態であること。こうした状態を改善し、子どもが自分で考えて行動できるようにすることが、家庭教育の大きな目的なのです。
【癇癪を減らすために親ができること】
家庭教育で重要なポイントは、「過干渉や過保護を避けること」です。
【自立心を育もう!】過保護・過干渉を知ることで癇癪解決や予防になります
子どもが成長し、自分の感情をコントロールできるようになるためには、次のようなアプローチが効果的です。
①「待つ」ことを覚える
子どもが困っているとき、すぐに手を出すのではなく、「自分で考えさせる時間」を与えましょう。自分の力で解決した経験が、自己肯定感を高め、癇癪を減らす一歩となります。
②感情表現をサポートする
子どもが癇癪を起こしたとき、「何が嫌だったのか」を一緒に整理してあげましょう。適切な言葉で感情を表現できるようになると、癇癪の頻度は大きく減少します。
③成功体験を積ませる
小さな成功でも構いません。「できた!」という達成感が、子どもの自立心を育てます。癇癪を乗り越える力をつけるためには、成功体験の積み重ねが欠かせません。
④ルールを明確にする
家庭内でのルールをしっかりと設定し、一貫した対応を心がけることも重要です。親が一貫性のある態度を示すことで、子どもも安心してルールを守ることができます。
【親がいなくなっても感情をコントロールできる子へ】
家庭教育の最終的な目標は、「親がいなくても自分で考え、行動できる子」に育てることです。特に癇癪の問題がある場合、自立心や感情のコントロール力を育むことが重要です。過干渉や過保護ではなく、必要なときにのみ寄り添いながら、子ども自身が解決策を見つけられるように子育てをしていきましょう。
【最後に】
今回の記事を最後までご覧いただいた上で、あなたのお子さんはいかがですか?
もし親がいなくなっても、お子さんは自分自身の力で感情をコントロールし、癇癪を我慢したり、自分の力で乗り越えていけるでしょうか。
家庭教育の在り方を見直すことは、子どもの未来を変える大きな一歩にも繋がります。
癇癪に悩む子どもが、自立した強い心を持つために、今親としてできることを考えてみましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。