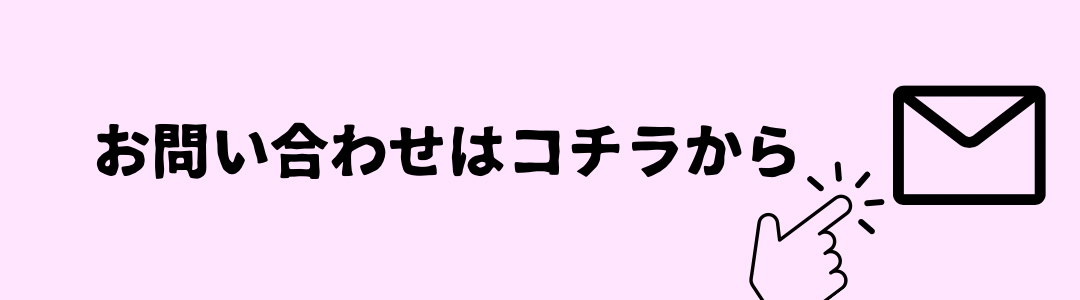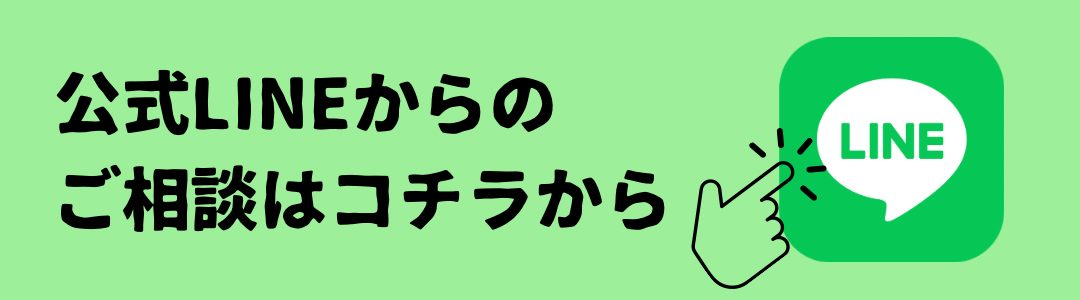【自立心を育もう!】過保護・過干渉を知ることで癇癪解決や予防になります
ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
今回は子育て中に必ず立ちはだかる壁、過保護・過干渉の線引きについてのお話しです。
癇癪が起こる原因については、これまでの記事でも触れてきました。
【癇癪に悩む親御さんへ】今、家庭内で出来ることを専門家が一緒に考えます
癇癪はお子さんの自立心を育むことで次第に減らすことや未然に防ぐための予防が出来ます。
「その自立心を育むことが難しいんだ!」と思う方もたくさんいるでしょう。
これまで子育てをされてきて難しいと感じてこられた親御さんでも、イメージと実践がしやすいように説明していきます。
【過保護・過干渉の線引きとは】
子育てをされている親御さんなら、必ず「過保護・過干渉になってはいけない」という言葉を見たり聞いたりしたことはあるでしょう。
色々な育児本を読んで勉強したり、ネットを調べてみたり、そして学んだ通りに過保護・過干渉をやめてみても「全然子育てが上手くいかない!」という親御さんと、私はたくさん出会ってきました。
何を持って過保護・過干渉になるのか?
何を持って必要な干渉と言えるのか?
正解は、「お子さんによって変わる」です。
兄弟がいるご家庭の子育てで例えてみます。
お兄ちゃんがここまで何も問題なく上手に育てることが出来たとします。
それでも、弟に対しても同じように子育てするのは実は間違いなのです。
兄弟であっても同じように育てるのは良くないとされています。
お兄ちゃんと弟は兄弟であっても、別の人間です。性格も違えば物事の受け取り方、考え方も違います。
お兄ちゃんには不要な干渉であっても、弟には必要。反対にお兄ちゃんには必要だった干渉でも、弟には不要ということも。
お子さんの傾向によって育て方は必ず変えていく必要があるのです。
・お子さん自身の現時点での能力
・年齢
・環境
・性格
これらの要素を複合的に考えて、「本当にこの子にとって今しようとしているアドバイスやお手伝いは必要なのか?」を考えて育てていくと、過保護・過干渉の線引きの感覚も次第に身についていきます。
マニュアルに沿ったような考え方は、子育てをする上では大変危険な考え方だというのが私の持論です。
【子どもの気持ちを知ることが大事】
過干渉=必ずしも悪いわけではありません。
過干渉というのは、お子さんのことを愛してやまない愛情深い親御さんが、我が子のために良かれと思い、愛するが故につい干渉してしまうと私は考えます。
しかし、子どもたちも保育園や学校に通い続けることで、体だけではなく心も成長していきます。
1歳、また1歳と年齢を重ねていく中で、親からの指摘やアドバイス、求めていないお手伝いをされてしまうと
「口うるさいなぁ」「面倒臭いなぁ」
場合によっては「もう親と離れて過ごしたい」という気持ちが次第に生まれてきます。
親に言われたからしてると思われるのが嫌だ
自分のことは自分でやりたい
自分のペースで進めたい
自分のことは自分で決めたい
いつまでも幼く扱わないでほしい
これらの気持ちに気付けずに、過保護・過干渉を続けた結果、お子さんの感情が爆発します。それが「もう何もかも嫌だ!!!」と癇癪や不登校に繋がるケースも少なくありません。
これまで「ママ!ママ!」だったお子さんでも、年齢を重ねるごとに上記のように考えるようになります。
寂しさや悲しさはあると思いますが、これが自立をしている途中段階であり、大事な一歩を踏み出そうとしている証拠なので「自分のことは自分でしたいんだな」と受け止めてあげましょう。
【過保護・過干渉の危険性】
今、ブログを読まれている親御さんも思い出してみてください。少なからず自分の親から口うるさくアレコレ指示された時に「うるさいなぁ」の気持ちが生まれたことはあるのではないでしょうか。
もちろん親御さんとしては、お子さんが困らないようにと考えた上での行動だと思います。
しかし、お子さんの年齢であれば自分で出来るはずの事に対して必要以上にアドバイスをしたり、手伝ってしまうと本来生まれるはずのなかった親への依頼心や依存心が強まってしまいます。それが母子依存や母子分離不安を起こしてしまい、自分の思い通りにいかないことがあれば癇癪を起こしたり、場合によっては「ママがいない学校には行けない」「ママがいないと不安」という思いから不登校や母子登校に繋がるのです。
自分で考える力、物事を決める力を使う経験を奪ってしまうと、自分一人で何かを決断することが出来なくなり、常に周りに答えを聞いたり頼ってしまったり、自分の力で生きていくことが難しくなるかもしれません。
そして決めてもらった上でも自分が納得しなければ癇癪に繋がり、いつしか全てに対して自分の思い通りに親に動いてもらうという子ども上位の親子関係になってしまうかも知れません。
過保護・過干渉の影響により、不満が爆発した場合でも癇癪や不登校に、不満がいつしか依存に変わっても癇癪や不登校に。
大袈裟ではなく、不要な干渉はこのような事態を引き起こしかねないのが現実です。
【最後に】
大事なのは、“今”のお子さんにとってその干渉は必要か不要かを見極めること。
自分でできることは自分でさせる。
親が何でも手を出すのは愛情ではなく甘やかし。
欲しがる物をなんでも与えるのは愛情ではなくて甘やかし。
甘やかしと愛情の違いをよく考えましょう。
この言葉を知ってる親御さんも多いのではないでしょうか。私はこの考え方のもと、日頃親御さんにアドバイスをさせていただいています。
「今してあげないと可哀想より、今甘やかすことによって将来自分で動けなくなる方が可哀想」という考え方で子育てをしてみてください。
きっと日頃されている子育て観が大きく変わり、その先にお子さんの成長が待っているはずです。
それでも線引きが難しい場合は是非ご相談ください。
「それはお子さんの性格に対して幼い対応です」
「それはお子さん自身の問題ですので、親御さんの手出しはグッと我慢しましょう」
「それはお子さんが自分1人では出来ないことなので手伝ってあげてください」
「それはこういう理由で過干渉です」
など細かくお子さんに合ったアドバイスをさせていただきます。
上手に過保護・過干渉の線引きをすることが、癇癪解決の鍵となり、癇癪を起こす前から親御さんがこの感覚を身につけると癇癪を未然に防ぐ予防にもなります。
是非一度、今回のブログ記事を意識して実践していただければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。