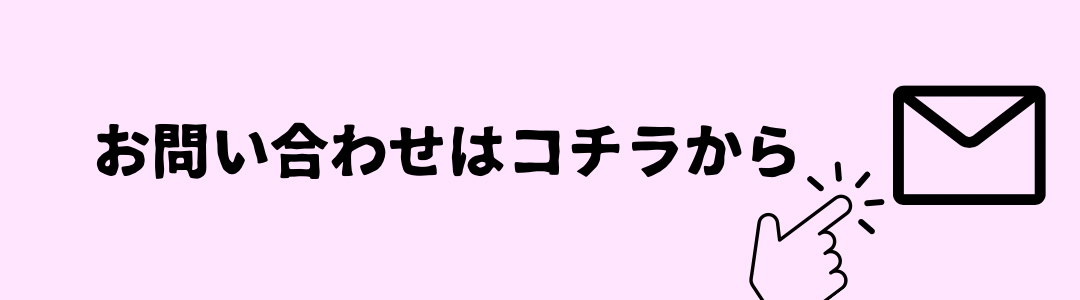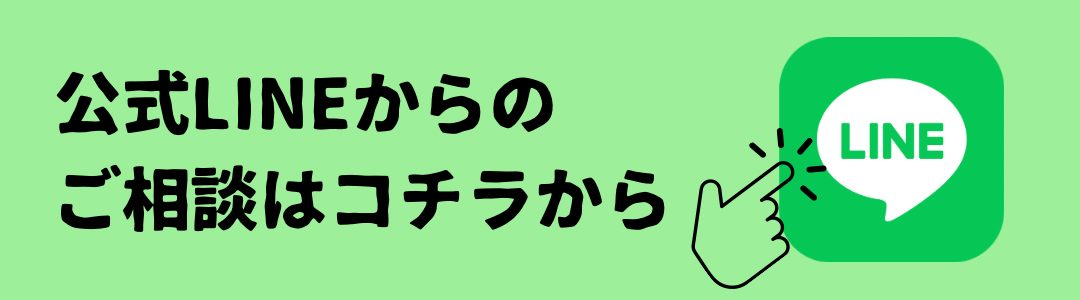【癇癪対応のコツ】親の焦りが子どもの情緒に与える影響と正しい向き合い方
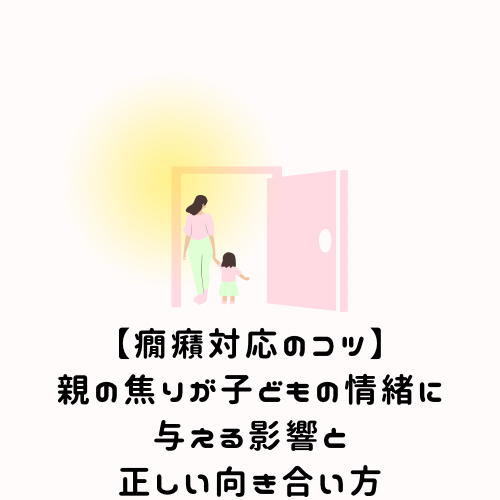
ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
子どもの癇癪(かんしゃく)に悩む親御さんは少なくありません。
突然泣き叫んだり、物を投げたり、時には暴れたりする姿を見ると「どう対応したらいいのか分からない」と戸惑ってしまいますよね。
今回の記事では、癇癪対応の専門家として、これまで多くのご家庭を支援してきた経験をもとに「癇癪対応で大切な親の心構え」ついて解説します。
結論から言えば、親の焦りが子どもの癇癪を長引かせてしまうことがあるのです。
【親が焦ると癇癪は悪化する?】
「なんとしても癇癪をやめさせたい」
「どうにか今すぐ落ち着かせたい」
そう願うのは親として自然なことです。
しかし、焦りから感情的に怒ったり、強く叱ったりすると、逆に子どもの不安や苛立ちを刺激し、癇癪が悪化してしまうケースが少なくありません。
一方で、冷静に状況を受け止めつつ、正しい対応を学びながら実践しているご家庭では、比較的早く子どもの情緒が安定していく傾向があります。
つまり、「癇癪をなくしたい」と焦る気持ちが、結果的に改善を遠ざけてしまうということなのです。
【癇癪対応の初期段階で大切なこと】
子どもの癇癪は、その子の気質や発達段階、生活環境によって原因が異なります。
そのため、対応の第一歩は「原因を見極め、家庭全体で土台を整えること」です。
具体的には以下のようなポイントがあります。
・子どもの気質や背景を理解する
・親子関係や生活リズムを整える
・親が正しい関わり方を学ぶ
支援の初期(1〜3ヶ月)は、子どもに直接的に働きかけるよりも、 親御さん自身が「癇癪への向き合い方」を学ぶことが最も重要です。
例えば、
・癇癪をどう受け止めるか
・どこまで介入するか
・どのような言葉をかけるか
こうした対応を習得することで、長期的に子どもの癇癪は落ち着きやすくなります。
逆に、親の焦りが大きいと冷静な判断ができず、せっかくのアドバイスを活かせないこともあります。
【「放っておけば良い」わけではない】
よくある誤解が、
「癇癪を起こしても落ち着くまで放っておけば良い」
という考え方です。
もちろん、過剰に反応しないことも大切ですが、それだけでは解決できないケースが多いのが現実です。
現代の子どもの癇癪は、
・不安感
・感覚過敏
・学校や家庭でのストレス
・発達特性
といった複雑な要因が絡んでいることが少なくありません。
だからこそ、ただ待つのではなく、焦らず・感情的にならず・正しい方法を学びながら対応する姿勢が欠かせないのです。
【親の心構えが子どもの情緒を安定させる】
癇癪対応で最も大切なのは、やはり親が焦らないこと。
子どもは自分でも抑えきれない感情や不安と戦っています。
その時に親が一緒になって感情的になると、子どもはさらに安心できなくなってしまいます。
だからこそ、親御さんは
・「冷静に学ぶ」
・「感情に巻き込まれない」
・「必要なら専門家に相談する」
という姿勢を持ってほしいのです。
癇癪対応の第一歩は「焦らずに学ぶこと」。
それが子どもの安心感につながり、結果的に情緒の安定を早めていきます。
【癇癪対応の第一歩は「親の焦りを手放すこと」】
・親の焦りは癇癪を悪化させることがある
・初期段階では「親が学ぶこと」が改善のカギ
・「放っておけば良い」ではなく、正しい対応が必要
・冷静な親の姿勢が子どもの安心感を支える
癇癪は一朝一夕でなくなるものではありません。
しかし、焦らずに取り組めば必ず改善へとつながります。
癇癪に悩む親御さんを支える専門家やカウンセラーは私たち以外にもたくさんいます。
決して一人で抱えずに、相談しやすい場所へ相談し、一歩ずつ、前へ進んでいきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。