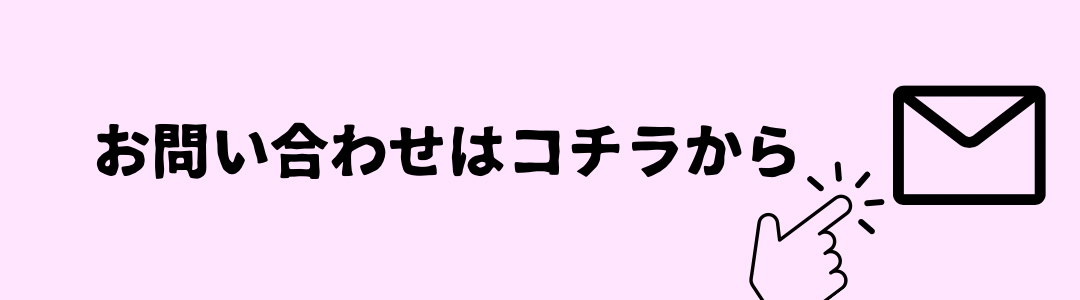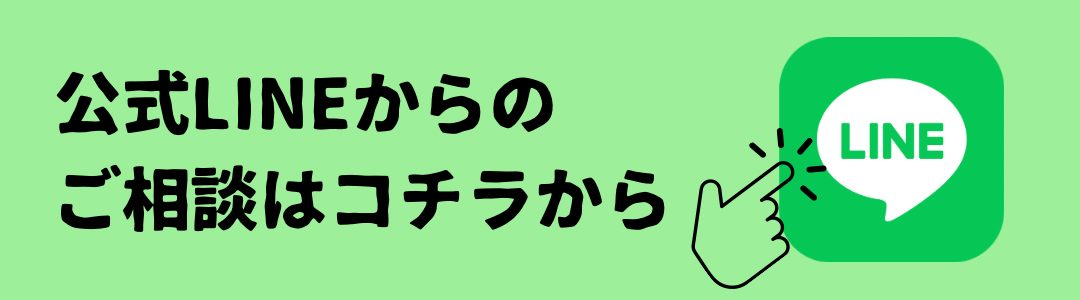【春休みの過ごし方】子どもの自主性を育む親の関わり方とは?
ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
多くのご家庭が春休みに突入するこの時期、お子さんの過ごし方に不満を抱えている親御さんが一定数いると推察されます。
「宿題もせずにゲームばかり…」
「生活リズムが乱れて朝起きるのが遅い…」
「ずっとスマホをいじっていて何もしない…」
このような悩みを抱えている親御さんは多いのではないでしょうか?
NEO PORTAには、癇癪の悩み相談が多いことはもちろんのこと、日頃の子育てに対しての相談もいただきます。
今回は、春休み中の子どもとの接し方や関わり方について、親子関係を良好に保ちながら、子どもが自主的に過ごせるようになるポイントをお伝えします。
【春休みは「親が干渉しすぎる時期」になりやすい?】
長期休みになると、子どもと過ごす時間が増えるため、つい「口を出しすぎる」ことが増えてしまいます。
例えば、こんな親子のやりとりをしたことはありませんか?
子:「…(ゲーム中)」
親:「もう!ゲームばっかりして!宿題はちゃんとやったの?」
子:「やってるよ!」
親:「全然進んでないじゃない!」
子:「(あとでやろうと思ってたのに…)」
このような会話が増えると、子どもは
「どうせ何を言っても怒られる」
「自分で考えるより先に言われる」と感じ、やる気を失ってしまうことも。
また、親が先回りして管理しすぎると、子どもの自主性が育たず、休み明けに「不登校」や「母子登校」になるなど、学校生活にも影響を及ぼすことがあります。
では、どうすれば春休みの過ごし方を子ども自身で考え、行動する期間にできるのでしょうか?
【春休みの子どもへの関わり方のポイント】
① 宿題は子どもの問題!親が管理しすぎない
「宿題は子どもがやるべきもの」と割り切ることが大切です。
親が「宿題やった?」と毎日言い続けると、子どもは「言われないとやらない」という習慣がついてしまいます。
もちろん、小学校低学年の場合は、スケジュールを一緒に考えたり、分からないところをサポートすることは大切です。しかし、基本的には見守る姿勢を意識しましょう。
② 生活リズムの乱れを防ぐには「朝のルーティン」を作る
長期休みはどうしても生活リズムが崩れがち。朝遅くまで寝てしまうと、昼夜逆転の原因になります。
おすすめなのは「朝のルーティン」を決めること!
・起きる時間を決める(遅くても8時までに起床)
・朝ごはんのあとに軽い運動や読書をする
・学習タイムを30分でも作る
夜更かしを防ぐために、スマホやゲームの時間を決めることも有効です。
③ 「ダラダラ時間」もスケジュールに組み込む
「ダラダラする時間=悪いこと」と思いがちですが、実は適度にダラダラすることも大切です。
例えば、
✔ 午前中は勉強や家の手伝いをする
✔ 午後はゲームや自由時間を楽しむ
このように「自由時間」と「やるべき時間」を明確に分けることで、メリハリのある生活を送れるようになります。
④ 「親子の時間」を意識的に作る
春休みは、普段忙しくてできない親子のコミュニケーションを深めるチャンス!年相応なコミュニケーションを意識してみましょう。
・一緒に料理をする
・公園で遊ぶ
・図書館や博物館に行く
・子どもの趣味(好きなアニメやゲーム)に付き合う
親子で楽しむ時間を作ることで、自然と子どもとの距離が縮まり、指示しなくても自発的に行動する力が育ちます。
【まとめ:春休みは「自主性」を育てる期間にしよう!】
春休みは、子どもが「自分で考えて行動する力」を伸ばす絶好の機会です。
✔ 宿題は子ども自身の問題と考え、管理しすぎない
✔ 生活リズムを整えるために、朝のルーティンを決める
✔ ダラダラ時間もスケジュールに入れてメリハリをつける
✔ 親子の時間を作り、コミュニケーションを深める
過干渉を減らし、適度な距離感を持つことで、子どもは「自分で考えて行動する力」を身につけていきます。
春休みを親子で楽しく、充実した時間にしていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。