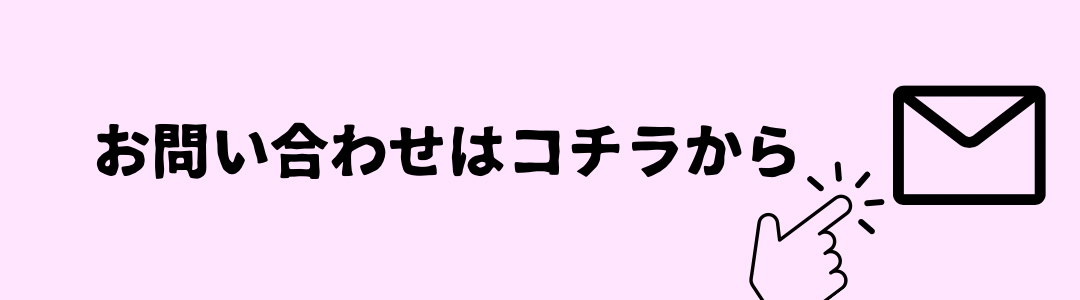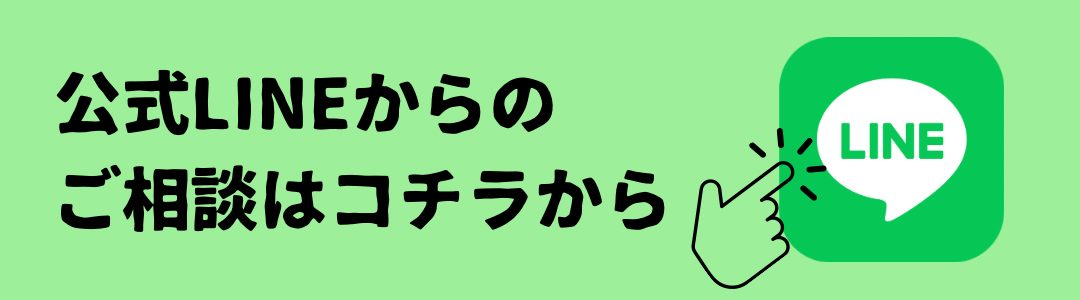【不登校の原因は癇癪かも?】子どもの心が叫ぶSOSと不登校との深い関係性
ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
「癇癪(かんしゃく)」という言葉を聞くと、多くの親御さんが「わがまま」や「一時的な反抗」と思いがちです。しかし、子どもが感情を爆発させる背景には、深い心の葛藤やストレスが隠れていることがあります。
不登校との関連性も見過ごせないのが癇癪です。今回の記事では、癇癪の特徴や原因、そして不登校との関係性について詳しく解説します。
【癇癪とは?わがままとは違う子どものSOS】
癇癪とは、子どもが感情をコントロールできなくなり、激しく怒ったり泣いたりする行動を指します。特に2~5歳の「イヤイヤ期」に多く見られますが、年齢が上がっても続く場合は注意が必要です。
癇癪の特徴的な行動
・怒りやすく、ささいなことで泣き出す
・物を投げたり、大声を出したりする
・他人や自分を傷つける行為に発展することもある
癇癪の主な原因
①ストレス
学校での人間関係、勉強のプレッシャー、家庭内の不和など、子どもの心を圧迫する状況。
②発達特性
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの特性が関係している場合も。
③感情表現の未熟さ
言葉で感情をうまく表現できない子どもが癇癪という形で感情を表すことがある。
癇癪は「わがまま」ではなく、子どもが助けを求めているサインだと理解することが大切です。
【不登校と癇癪の意外な関係】
日本では不登校の子どもの数が年々増加しており、その背景には多くの要因が絡んでいます。その中で、癇癪を繰り返す子どもは、不登校になるリスクが高いことが分かっています。
私自身、NEO PORTAとは別で、不登校の子どもたちを復学支援に導く“復学支援”の会社を経営していますが、癇癪と不登校の複雑な関係性を何度も目の当たりにしています。
①ストレス発散の不十分さ
癇癪を起こす子どもは、学校生活で感じた不安やストレスを適切に発散できないことがあります。その結果、ストレスが蓄積し、学校を避けるようになります。
②自己肯定感の低下
癇癪が原因で叱られることが増えたり、周囲に理解されなかったりすると、「自分はダメだ」と感じるようになります。この自己否定感が学校への抵抗感につながることも。
③人間関係の悪化
癇癪を繰り返すことで友達や先生との関係が悪化し、「学校は嫌な場所」という認識が強まり、不登校に至るケースもあります。
【親ができる癇癪と不登校の予防対策】
癇癪を理解し、適切に対応することで、不登校を予防する道が開けます。以下に具体的な方法を挙げます。
①子どもの感情に寄り添う
まずは、子どもの気持ちに共感しましょう。
「嫌なことがあったんだね」「辛かったね」と言葉にするだけで、子どもは安心感を得られます。
②癇癪のきっかけを探る
癇癪が起きる原因や環境を把握するために、日記や記録をつけましょう。具体的な引き金(学校の出来事、家庭内の変化など)を特定することで、効果的な対策を講じることができます。
③ストレス発散の場を提供する
スポーツやアート、自然体験など、子どもが感情を発散できる活動に参加させましょう。ゲームは癇癪のきっかけになりやすいので、なるべくゲーム以外で趣味となることを探せるのが良いです。主に体を動かすことで心の安定が得られることも多いです。
④専門家の力を借りる
癇癪や不登校が続く場合、心理士や発達支援の専門家に相談することが重要です。発達障害が関係している場合、専門的な対応が必要になることもあります。
【癇癪は子どもの心の叫び】
癇癪は単なる「わがまま」ではなく、子どもの心が発するSOSのサインです。その背景を理解し、適切に対応することで、不登校やさらなる問題を未然に防ぐことができます。
一度不登校になると、子ども自身だけではなく家庭全体で相当な負荷がかかります。
親として子どもに寄り添いながら、必要であれば専門家の力を借りることを恐れずに。癇癪を抱える子どもが安心して成長できる環境を作るのは、親御さん、そして私たち大人の役目です。
癇癪に悩んでいる方も、すぐに改善することは難しいかもしれませんが、小さなステップを積み重ねていくことで、感情コントロールが可能になり、それが不登校の予防にも繋がります。
癇癪の対応や子育て全般にお困りの方は、遠慮なくNEO PORTAにご相談ください。
各ご家庭に合わせたアドバイスで、必ず解決できます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。